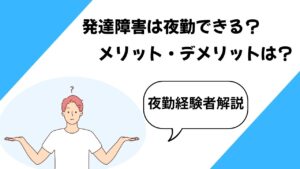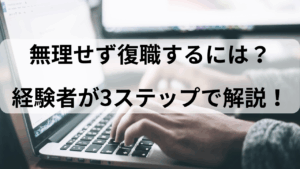うつ病や適応障害と診断された人の背景には、原因として発達障害がある場合も多いです。発達障害がきっかけで、他の精神疾患にかかることを「二次障害」といいます。
筆者も二次障害に悩まされ、10年間でうつ病や適応障害を3度発症しました。その度、復職して試行錯誤する中で、病気との付き合い方がだんだんとわかってきたのです。実際に体験したからこそわかったことを、余すことなくお伝えします。
本記事を読めば、二次障害の理解が深まり、体調を崩さず働くポイントが見つかります。ぜひ最後までお読みください。
二次障害とは
二次障害とは、発達障害が原因で起こる精神疾患や行動のことです。発達障害を抱えている人は、以下の理由からストレスがたまりやすい傾向があります。
- コミュニケーションが苦手
- 環境の変化についていけない
- 過集中による疲労
- 周りの意見や期待に過剰に合わせてしまう
ストレスや周囲に馴染めない環境が長く続くと、精神疾患や問題行動を引き起こしやすくなります。ただし、全ての発達障害の人が二次障害を発症するものではありません。周囲の理解やサポート、本人の工夫があれば、二次障害を回避できます。
内在化障害
発達障害によって引き起こされる二次障害は、内在化障害と外在化障害の2種類に分類されます。
内在化障害とは、自分自身に影響を及ぼす障害のことです。例は以下のとおりです。
- うつ病
- 適応障害
- 不安障害
- 強迫性障害
- 依存症
- 心身症
- 不登校・引きこもり
一人で悩みを抱え込むため、周りからは問題がないように見える傾向があります。二次障害を発症してから初めて、発達障害だったことに気づくことも多いです。
外在化障害
外在化障害とは、他者に影響を及ぼす障害のことです。
- 反抗挑戦性障害
- 行為障害
- 暴力
- 家出
- 非行
反抗挑戦性障害とは、年齢に合わない反抗的な態度や行動を、大人や周りの人に行う障害です。また、行為障害は、他人の権利を侵害したり、社会のルールをたびたび破ったりする行動が繰り返される障害で、主に思春期に現れることが多いとされています。
内在化障害と外在化障害の両方が、同時に現れることもあります。
二次障害が起きた時の対処法
二次障害が起きた時は、無理をせず以下の流れに沿って対処しましょう。
- 病院で診察を受ける
- 治療に専念する
- 回復後も定期的に病院に通う
病院で診察を受ける
まずは病院で主治医の診察を受けましょう。主治医はあなたの発達特性や性格などを理解しており、二次障害への適切な対処法を教えてくれるからです。
まだ、かかりつけの病院がない場合は、精神科や心療内科を受診しましょう。
治療に専念する
主治医の指示に従い、治療に専念しましょう。うつ病や適応障害などの精神疾患になった場合、休職を勧められることもあります。十分に治るまでは仕事をしないことが大切です。
休職しても症状が十分に回復しないまま復職すると、症状が悪化し再び休職になるケースが少なくありません。
厚生労働省が2004年に発表した「うつ対応マニュアル-保健医療従事者のために-」では、うつ病の再発率について、以下のように報告されています。
いったん改善しても約60%が再発しますし、2回うつ病にかかった人では70%、3回かかった人では90%と再発率は高くなります。
二次障害の中でも、うつ病は再発しやすい病気です。再発を防ぐためにも、時間をかけて治療に専念しましょう。
回復後も定期的に病院に通う
復職した後でも病院に通い、主治医の診察を受けましょう。復職直後は、会社の人とのコミュニケーションや仕事をこなすことに体力を使ってしまい、自分の想像以上にストレスがかかるからです。
筆者は、主治医と話す時は以下の内容を考えていました。
- 最近の調子はどうか
- どうして調子が悪いのか(調子が悪い場合)
- 原因はどこにあるか
上記の内容を話すことで、主治医から具体的なアドバイスをもらえます。
ただし、精神科の診察は約5分と短いです。相談したい内容がうまく話せなそうなときは、今日相談したいことをメモに書いておき、診察時に主治医に渡す方法もあります。
主治医はそのメモを見て、患者の相談を聞いてくれます。
二次障害を引き起こさないための5つの予防策
二次障害の症状が落ち着き、心に余裕を持てるようになったら、二次障害を引き起こさないための予防策についても考えましょう。筆者の体験も交えながら、詳しく解説します。
- ストレスがたまる前に休む
- 生活リズムを整える
- 本や動画でストレス対処法を学ぶ
- 自分の発達特性を理解する
- コミュニティに参加する
ストレスがたまる前に休む
予防策1つ目は、ストレスがたまる前に休むことです。発達障害の人は、人間関係のストレスや環境の変化に敏感で、気付かないうちにストレスをためこみやすい傾向があります。
具体的な対策は以下のとおりです。
- 休憩時間になったら、職場の人に声をかけてもらう
- 有給休暇を取る
- 会社や自宅で一人になれる場所を見つける
- 仕事後の趣味を作る
- イヤーマフやノイズキャンセリングイヤホンを使用する
休憩時間になったら、職場の人に声をかけてもらう方法は、過集中を防ぐ効果があります。イヤーマフやノイズキャンセリングイヤホンを使うと、周囲の環境音を軽減し、作業に集中しやすくなります。
ただし、イヤーマフやノイズキャンセリングイヤホンを職場で使う場合は、職場の上司に問題ないか必ず確認をとりましょう。
生活リズムを整える
予防策2つ目は、生活のリズムを整えることです。発達障害の人は作業に没頭すると、時間を忘れて続けてしまう傾向があります。
その結果、夜更かしをしてしまい、徐々に生活リズムが乱れてしまいます。
例えば、朝は決まった時間に起き、朝日を浴びるようにしましょう。
筆者は、夜21時以降は、スマホやパソコンなどのデジタル機器に触らないようにしています。夜遅くにデジタル機器を触ると眠れなくなるからです。
また、朝は二度寝を防ぐために、起きたらすぐ散歩するようにしています。
本や動画でストレス対処法を学ぶ
予防策3つ目として、本や動画でストレスの対処法を学びましょう。ストレスの対処法を知っておくと、トラブルが起きても落ち着いて対処可能です。
例えば、上司から「今月までにお願いします」といった曖昧な指示を受けた時、発達障害の方は「期限はいつまでか」と悩んでしまいます。
曖昧な指示をもらったとき「30日の13時までに提出でいいですか」と確認すると、期日が明確になり、作業に集中できるでしょう。
本や動画では、こうした対処法が学べます。実践でいつでもできるように練習しておきましょう。
自分の発達特性を理解する
二次障害の予防策4つ目は、自分の発達特性を理解することです。発達特性とは、自分の得意不得意や、ストレスがたまりやすい環境などのことです。
例えば、筆者の場合は以下の得意不得意があります。
- 得意なこと:言葉の意味や表現の理解
- 苦手なこと:人が話した内容を忘れる・毎日のルーティンが崩れると体調を崩す
自分の得意不得意を把握できると、自分でもストレスをためない工夫ができるようになります。筆者の苦手なこと「人の話をすぐ忘れる」の場合は、以下の対策があります。
- メモを取る
- メモが取れない場合は、ボイスメモを使う
自分の発達特性を理解して、ストレスをためない工夫をしましょう。
コミュニティに参加する
最後の予防策は、コミュニティに参加することです。
コミュニティとは、共通の悩みを抱える人々が集まり、お互いの体験や感情を共有する場のことです。「自助会」と呼ばれることもあります。
筆者は発達障害の自助会に参加していました。筆者が悩んでいる内容に、自助会のメンバーが答えてくれて悩みが解決したこともあります。
現在は、オンラインで無料開催されているところも増えているので、自宅にいながら気軽に参加できます。
自助会については、以下の記事に詳しく書きました。あわせてお読みください。
発達障害と診断されたときの受け入れ方|怒りから向き合うまでの体験談
二次障害が起きたときに相談できる施設3選
発達障害や二次障害で困っている場合は、以下の施設で相談ができます。日常の困りごとから就労支援に関することまで幅広く対応しています。
- 発達障害者支援センター
- 就労移行支援・就労継続支援事業所
- 障害者転職エージェント
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障害者の支援を行う機関です。各都道府県や各政令指定都市に1か所以上設置されており、無料で利用できます。
具体的な支援内容は以下のとおりです。
- 発達障害者やその家族の相談
- 発達障害者の就労支援
利用する場合は、各市町村の福祉課に「障害福祉サービス受給者証」を申請しましょう。
就労移行支援・就労継続支援事業所
障害者就業・生活支援センターとは、障害者の自立や雇用の促進・安定を目指して全国に設置されている機関です。令和7年6月時点で全国に339箇所設置されています。
相談できる内容は以下のとおりです。
- 就労支援
- 職場定着支援
- 生活全般の支援
- 就職活動のサポート
職業定着支援では、就職後も働き続けられるようにサポートが受けられます。また、生活支援では、日常生活の悩みや障害年金の申請も可能です。
障害者手帳がなくても無料で利用できます。
障害者転職エージェント
障害者転職エージェントとは、障害のある方の転職を支援する民間のサービスです。発達障害の人でも利用でき、主に以下の支援を行っています。
- 書類作成
- 面接対策
- 入社後の定着支援
転職に特化した手厚いサポートが受けられます。無料で利用でき、障害者転職エージェントによっては各都道府県に1か所ずつ施設が用意されているため、通いやすいのもメリットです。
二次障害の対策に迷ったら職場環境を変えるのも視野に
二次障害は、発達障害が原因で起こる精神疾患や行動のことです。さまざまな症状がありますが、自分自身に影響を及ぼす「内在化障害」と他者に影響を及ぼす「外在化障害」の2つに分かれます。
二次障害を起こした場合は、精神科や心療内科に行った後、十分な休養をとり、予防策を考えましょう。
ただし、どんなに対策をしても職場の環境によって、二次障害が引き起こされる可能性があります。
職場の環境を変えたい場合は、障害者専門の転職エージェント「DIエージェント」がおすすめです。
DIエージェントでは、専属カウンセラーが求人の提案や書類作成、面接対策など転職活動全般のサポートをしています。
また、障害者向け求人では難しいとされてきたキャリアチェンジ・キャリアアップで、年収がアップした事例もあります。
正社員求人や大手企業求人も多数あります。
「二次障害で転職しようか考えている」「障害でも一般企業の就職を諦めたくない」という方は、DIエージェントの活用を検討してみてください。