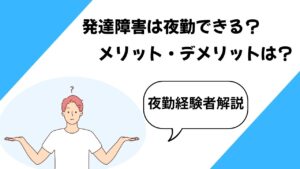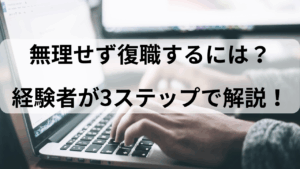発達障害と診断されたとき、障害をどう受け入れればいいのか悩む人は多いようです。筆者も例外ではありませんでした。
筆者は、27歳の時に発達障害(ADHD/ASDグレー)の診断を受けました。当時は、診断が受け入れられなくて怒りっぽくなり、周囲の人を怖がらせてしまったことを反省しています。「これからどう生きていけばいいんだ」と絶望していた時期もありました。
しかし、自助会が筆者に発達障害と向き合う機会を与えてくれました。自助会とは、同じ障害を抱えている人が集まり、生きづらさや孤独感を分かち合う場です。
同じ障害を持つ仲間と共に自己理解を深め、障害を乗り越える方法を共有したことで、だんだんと障害を受け入れられるようになったのです。今では発達障害も個性の一部だと思っています。
本記事では、筆者が発達障害と診断されてからその事実と向き合うまでの体験談を紹介します。診断を受けて気持ちの整理がつかない人が、少しでも前向きな気持ちになる助けになれば幸いです。
リワーク中に「発達障害かもしれません」
筆者が発達障害を疑われたのは、うつ病で休職して医療リワークに通っているときです。医療リワークとは、医療機関で行う復職プログラムのことです。
リワークスタッフの心理師から、個別に話をされました。
「村木さんは発達障害の疑いがあります。」
話を聞くと、リワーク中の発言や行動に発達障害の特徴が見られると感じたそうです。また、うつ病を発症する背景には、発達障害が隠れている場合もあると教えてくれました。
これまで発達障害の方を見てきた心理師が言っているため、とても信頼ができました。また、うつ病の原因が発達障害かもしれない点が、とても気になったのです。
検査を受けるのは自由ですが、自分をより深く知りたい気持ちから受けることにしました。
診断されるまでの流れ
発達障害の検査は、正式に診断されるまで約1ヶ月かかります。診断までの流れは以下のとおりです。
- インテーク面談
- 知能検査
- 診断
インテーク面談
インテーク面談とは、診断前に行われるヒアリングのことです。具体的には、本人が困っていることや、生育歴などを心理師に話します。
幼少期の性格を話す必要があるので、母子手帳や小学校の成績表などがあると正しい診断の手助けになります。
実際の面談では、質問形式で話が進みました。心理師がリワークのスタッフだったこともあり、筆者の場合は緊張することもなく面談を終えられました。
知能検査
発達障害の知能検査には、さまざまな方法があります。筆者はWAIS-IV(ウェイス・フォー)という検査をしました。
心理師が質問してくる言葉の意味に答えたり、サイコロ型のブロックを使って紙に書かれた図と同じ形にする検査などがあります。
筆者はサイコロ型のブロックを使って紙に書かれた図と同じ形にするのが苦手で、1つの問題に3分以上かかっていました。
心理士の方は「焦らないで良いですよ」と声をかけてくれました。しかし、簡単と思っていた問題ができず、焦ってしまっていたことを今でもよく覚えています。
検査は1時間ほどで終了し、どんな結果になるんだろうと不安な気持ちになりました。
診断
知能検査から1週間後、結果を聞くために病院の精神科に行きました。受付で「内容を詳しく解説するので、診察の順番は一番最後になります」と伝えられました。
待合室の人が少なくなるなか、筆者はどう診断されるのか常に緊張しっぱなしです。
ようやく名前を呼ばれて、診察室に入ると先生が「こんにちは」と明るく挨拶をしてくれました。
先生は結論から話し「ADHD/ASDグレーゾーンです」と診断しました。筆者は障害と診断されたことが衝撃で、頭が真っ白になったのです。
先生とは、検査の結果や今後のリワークで意識する点など色々話しましたが、ほとんど内容が頭に入ってきませんでした。
診断後は受け入れらなかった
診察から日が経つにつれて、だんだんと自分自身に怒りを感じるようになりました。学生時代、人間関係がうまくいかずいじめられたり、周囲から避けられたりしていたからです。
発達障害の本を購入してわかったのですが、発達障害持ちの人は、人間関係の悩みが少なくないようです。
人間関係がうまくいかなかった原因が発達障害だとわかったとき、当時の苦しかった思いがフラッシュバックしました。「もっと早く診断されていれば、こんなに苦しい思いをすることはなかったのに」と悔しかったです。
また、発達障害が完治できないものと知ったときは、これからどう生きていけばいいのかと絶望しました。
みんなそれぞれ悩みを抱えている
怒りが収まらないなか、精神科の先生から「発達障害の自助会に参加しませんか?」と提案されました。
筆者は、同じ障害を抱えている人はどんな悩みがあるんだろうと興味をもち、参加することにしました。
自助会に参加していたメンバーは筆者以外に4人いました。
- 前職でうまくいかず、障害者枠で就職しようとしている女性
- 上司の話がうまく理解できない男性
- 片付けがうまくできない主婦
- こだわりが捨てられない男性
参加者は筆者と同じ障害を抱えていましたが、悩んでいることはそれぞれ違います。
自助会では、生活や仕事での困りごとの解決手段をみんなで話し合ったり、お互いの夢について語り合ったりしました。
悩みはすぐに解決するものではありません。しかし、みんなが悩みを抱えつつも、前を向いて生きている姿を見て「苦しいのは自分だけではないんだ」と心を動かされました。
また、自助会のメンバーは、筆者の話にも親身になって話を聞いてくれました。次第に、自分にも居場所があると感じ、怒りはおさまっていったのです。
発達障害は「個性」と考える
筆者が、発達障害を個性と考えられるようになったのは、自助会で悩みを話しているときです。
どんな話をしたのかよく覚えていませんが、他のメンバーから「素直ですね」「努力家ですね」と声をかけてもらったのです。
筆者にとっては当たり前のことだったので、はじめは謙遜をしていました。しかし、素直さや努力家の指摘は、過去に褒められていたことであるのを思い出しました。
また、他のメンバーの話を聞くうちに、その人ならではの強みがあることがわかったのです。
このとき「自分の強みは誰にでもあるものではないんだ」「相手が褒めてくれたのは自分の個性なんだな」ということに気づきました。それ以来、相手の話を素直に聞き、いいところを積極的に話すようにと今も心がけています。
発達障害には、欠点もあります。しかし、同時に自分だけの強みでもあるのです。
1人で悩まず自助会に頼ろう
発達障害と診断されたときは、誰でもショックを受けるでしょう。また、悩みが自分で解決できない場合、ますます苦しくなります。
そんなときは、ぜひ自助会に頼ってください。現在、自助会は病院だけではなく、オンラインでも気軽に参加できるようになっています。
筆者は、もともと人と関わるのが苦手なタイプです。しかし、自助会に参加したことで「人の痛みを癒すのもまた人なんだ」と実感しました。
筆者の体験が、読者の皆さんが自分を好きになるきっかけになれば幸いです。