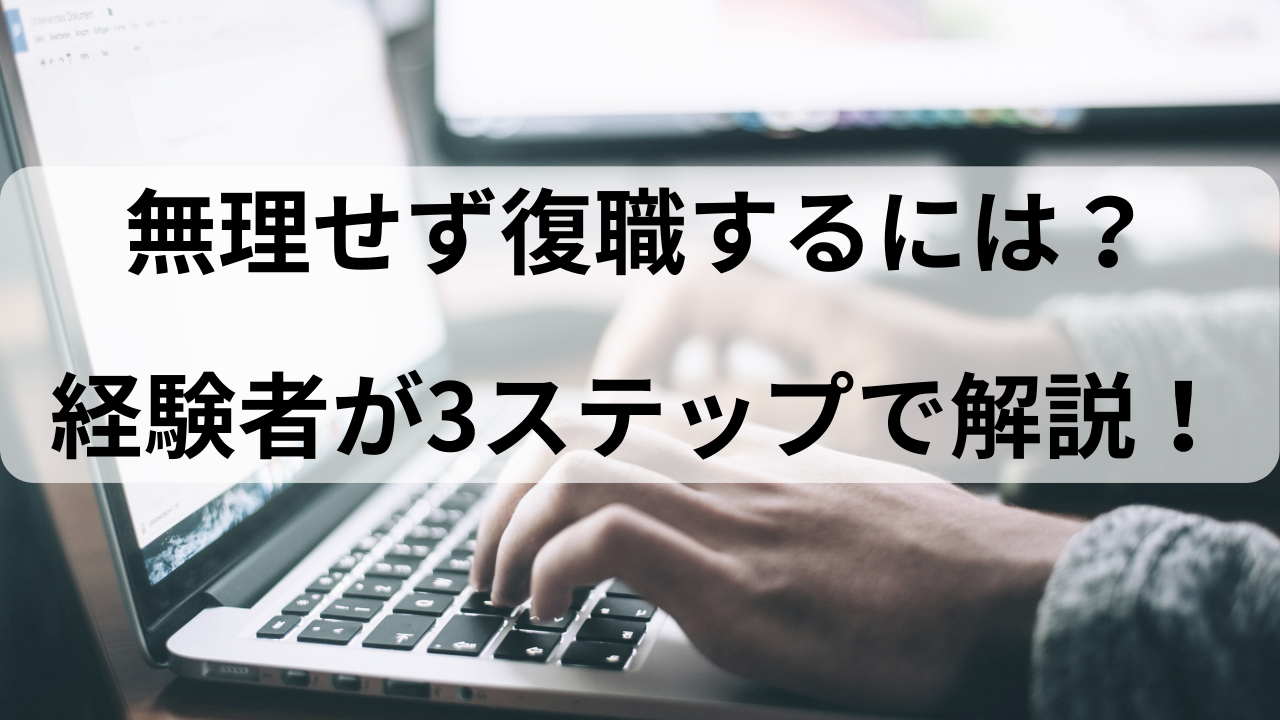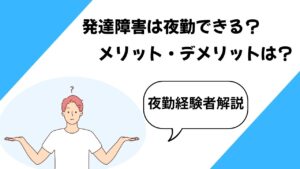初めてうつ病になって休職した際に、「復職する方法がわからない」「会社から復職の方法の説明を受けたけれどよく理解できない」と悩む方は多いです。
実は筆者もうつ病で1年間休職した経験があるのですが、復職の方法はわからないままでした。ですが、復職のステップを1つずつクリアすることで、私も無事復職できました。
本記事では、無理せず復職する方法を経験者の目線で解説し、復職後も長く働くための注意点も紹介します。記事を読むことで、自分のペースで焦ることなく復職でき、長く働けるようになります。ぜひ最後までお読みください。
うつ病から復職にかかる平均休職期間
うつ病や適応障害で休職した場合、体調が良くなったと感じても復職には時間がかかります。2015年の「民間企業における長期疾病休業の発生率、復職率、退職率の記述疫学研究」で1550人を対象とした研究では、休職からの期間ごとの復職できる確率は以下のとおりでした。
- 3ヶ月:35%
- 6ヶ月:58%
- 12ヶ月:71%
- 18ヶ月:75%
休職から3ヶ月で復職できるのは約35%で、時間をかけるほど復職率は高まります。
「上司や同僚にかけてはいけない」「収入が減る」などの理由から、症状が残っているのに職場に復帰し体調が悪化し、再休職になってしまった事例もあります。
病気の回復には個人差があるため、周りの人と比較しないことが大切です。復職には時間がかかるものと考えましょう。
うつ病から復職までの3ステップ
うつ病から復職までのステップを筆者の経験も交えながら解説します。具体的には以下の3ステップです。
- 療養期
- 復帰準備期
- 会社面談・職場復帰
療養期
うつ病になった初めの頃は、まだ症状が強く残っています。まずは服薬と好きなことをしつつ、十分な休養をとりましょう。
症状が落ち着いたら、生活リズムを整え、通勤時の生活リズムに戻しましょう。
筆者の場合、休職前と同じく6時に起き、夜22時に寝るという生活をしていました。日中は、近所の散歩やゲーム、家事の手伝いなどをして、仕事のことは一切考えずに生活していました。
休職しても職場が近く、思うように休めない人もいます。その場合は、実家に戻って療養する方法もあります。
しかし、休職期間中でも定期的に会社と連絡を取る必要があるため、実家で過ごす場合は会社に確認してから戻りましょう。
復帰準備期
うつ病の症状が落ち着いたら、復帰準備期に入ります。具体的には週5日、1日8時間会社で働くのと同じ程度の負荷に耐えられるようにしましょう。
また、再休職にならないために、休職の原因の振り返りが大切です。筆者は復帰準備期には以下のことをしました。
- 生活リズムを保つ
- ストレスを受けた時や環境を振り返り予防策を考える
- 図書館などを利用し仕事の時間帯は外出する
- 予防策をパソコンにメモしておく
休職に至った理由の振り返りは、自身が思っている以上にストレスがかかります。最初のうちは、図書館に1日行ったら2日休む、3日行ったら4日休むといったペースで大丈夫です。
継続することで体力や集中力が少しずつ戻るため、日中の活動量も次第に増えていきます。
復職準備を続け、自信がついたら主治医に相談し、職場復帰可能か判断してもらいましょう。
会社面談・職場復帰
主治医が職場復帰可能と判断した時、復職診断書を書いてもらい、職場に提出します。会社や産業医、保健師などが立ち会い、復職後の働き方について相談します。
例えば、復職後1ヶ月間は残業をしない、時短勤務にするなどの相談も可能です。もし、別の部署に異動したい場合も、面談時に相談しましょう。
復職の具体的な日程が決まれば、職場復帰が実現します。
うつ病からの復職を支援する「リワークプログラム」
リワークプログラムとは、施設に通い復帰準備をする方法です。毎朝通うため、生活リズムを安定させたり、他の休職者や施設の方とコミュニケーションの練習ができたりと、働く環境に近い状態で復帰準備を行います。
リワークプログラムには、主に以下の3つの形式があります。
- 医療リワーク
- 職リハリワーク
- 民間リワーク
医療リワーク
医療リワークは、精神科クリニックや病院が運営しているリワークプログラムです。
目的は再休職予防です。生活記録表で生活リズムを調整したり、自分の考え方のクセやストレスの原因も見つめ直したりします。
リワーク終了までにかかる期間は、約半年〜1年です。休職者の体調によって、期間の長さにはバラつきがあります。
筆者は医療リワークに通った経験があります。利用者と交流することで自分で休職になった振り返りをするよりも深く自分の特徴を知ることができました。
毎日通うことになると費用面が気になりますが、自立支援医療の申請をすると支払いが1割で済みます。月ごとに自己負担額の上限も決まっているため、医療費を安く抑えられます。
医療リワークを受けたい場合、最初の診察日を予約する必要があります。
精神科は初診の場合、1ヶ月後以降になることも多いため、医療リワークを考えている方は早めに予約してください。
職リハリワーク
職リハリワークは、各県に設置されている地域障害者職業センターが運営しているリワークプログラムです。職場復帰支援の名目で実施されています。
目的は、職場への適応に向けた本人と雇用主への支援です。
具体的には、パソコン業務で集中力を回復したり、無理なく働ける方法を見つけたりするなどのプログラムがあります。
また、職業カウンセラーが雇用主に復職後の環境調整や配慮を促してくれるのも特徴です。それにより、休職者が復帰した後に長く働き続けやすくなります。
費用は無料ですが、公務員は利用できません。
人気があるため、申し込みから開始までに2ヶ月以上待つ場合もあります。
民間リワーク
民間リワークは、民間企業が提供しているリワークプログラムです。民間リワークの特徴は、現在失業している人でも、復職意欲があれば参加できる点です。
目的は、安定して職場に復帰できるように支援することです。他のリワークとの違いは、プログラムの自由度の高さです。
心理教育や生活習慣改善だけでなく、農作業やカヌー体験など独自のプログラムを設定している企業もあります。初めての体験をすることで、新しい働き方が見つかる場合もあります。
福祉制度を利用すれば、費用の自己負担を1割に抑えられます。利用者の前年度の収入に応じて、月に支払う金額の上限(0〜37,200円)が決まります。
うつ病から復職後の注意点3選
復職はゴールではなく、新しいスタートです。うつ病の再発や再休職を防ぐには、復職後1ヶ月間の過ごし方がとても大切です。とくに以下の3点に注意しましょう。
- 休職中の生活リズムを守る
- 7〜8割の力で仕事をする
- 通院を続ける
休職中の生活リズムを守る
復職後は、起きる時間や寝る時間など休職中の生活リズムを崩さないようにしましょう。生活リズムが崩れると、体や心のストレスの原因になり、疲れが溜まりやすくなります。
休日は疲れてしまい昼過ぎまで寝たい方も多いです。しかし、昼過ぎまで寝ると生活リズムが狂う原因にもなるため、普段の起床時間から+1時間以内に起きるようにしましょう。
他にも、「運動する」「サラダを食べる」といった休職中の健康的な生活リズムを継続するのは、難しいものです。
その場合「5分ストレッチをする」など目標のハードルを下げて、できることからやっていきましょう。
7〜8割の力で仕事をする
復職初めは、7〜8割の力で仕事をすることを意識しましょう。今まで休んでいた分、遅れを取り戻すかのように全力で働くと、再び体調が悪化する可能性があります。
また、同じ部署で戻り慣れている職場でも、復職直後はストレスや疲労が溜まりやすいです。
職場の環境に体が慣れた後で、少しずつパフォーマンスを上げていきましょう。
通院を続ける
復職した後も、通院は続けましょう。特に復職から1年間は、疲労の蓄積や精神的疲れも感じやすく、気分が落ち込む人が多いです。
体調に不安を感じる場合は、主治医や必要に応じてカウンセリングを受けましょう。
また、再休職したくないと我慢する方もいますが、不調を訴えてもすぐに再休職になるわけではありません。
不安な時は一人で悩まず、周りの力を積極的に頼りましょう。
うつ病で転職を検討する際のポイント3選
うつ病になり、休職した方の中には転職したほうがいいのではと考える方もいるでしょう。しかし、すぐに転職を考えるのはよくありません。
ここでは、転職を検討する際のポイントを紹介します。
- 退職するかは症状が落ち着いてから考える
- ひとりだけで考えず人に相談する
- 障害者向けの転職エージェントを活用する
退職するかは症状が落ち着いてから考える
うつ病の症状が落ち着いてから、転職や退職を考えましょう。うつの症状が強いと「上司や同僚に迷惑をかけている」などのネガティブな考えになりやすく、結論を急いでしまいます。
筆者もうつ病で休職した時は症状が強く退職を考えていましたが、症状が軽くなるにつれて、退職以外にもさまざまな選択肢があることがわかりました。
- 部署異動
- 職場の環境調整
- ストレス対処法
後悔しないためにも、転職や退職はうつ病の症状が落ち着いてから考えましょう。
ひとりだけで考えず人に相談する
ひとりで転職や退職のことを考えると、ストレスもかかりますし、ネガティブな考えにもなりやすいです。そんな時は、周りに相談しましょう。例えば、以下のような人に相談するのがおすすめです。
- 主治医
- 会社や産業医
- 家族や友人
主治医に相談すると、リワークの紹介や仕事の配置換えは可能かどうかのアドバイスがもらえます。会社や産業医に相談すると、職場環境が改善される可能性がありますし、家族や友人と話すと考えが整理されます。
悩んでいる場合は、ひとりで悩まず周りに相談することで、ストレスを減らしていきましょう。
障害者向けの転職エージェントを活用する
うつ病の症状が落ち着き、周りに相談したうえで転職や退職を選ぶ方もいます。しかし、ひとりで転職活動をしていると、病気を抱えながら転職が成功するのか不安になることがあります。
そんな時は、障害者向けの転職エージェントを利用するとよいでしょう。
なかでも、障害者向け転職サービス業界No.1の転職エージェントである「atGP」はおすすめです。キャリアプランナーが利用者の希望条件や障害の状況を聞き、利用者に合った仕事を紹介してくれます。
また、20年のサポート実績を活かした、志望動機や自己PRなどの面接対策も受けられます。
オンラインや電話、対面で無料で相談できるため、長く働ける職場を見つけたい方はatGPを活用してみてください。
まとめ
復職する流れは「療養期」「復帰準備期」「会社面談・職場復帰」の3ステップに分かれます。「会社面談・職場復職」の段階に移る際には、主治医に職場復帰が可能であると診断を受ける必要があります。復職準備期で自信が付いたら、主治医に相談しましょう。
復職した際には、休職中の生活リズムを保ち、普段の7〜8割の力を意識することで、長く働くことができます。
病気の回復や復帰準備の期間は人によって異なります。筆者もうつ病で1年休職した時は、いつ復帰できるのか毎日不安でした。
しかし、一歩ずつステップを踏めば、復職も見えてきます。自分のペースで頑張りましょう。